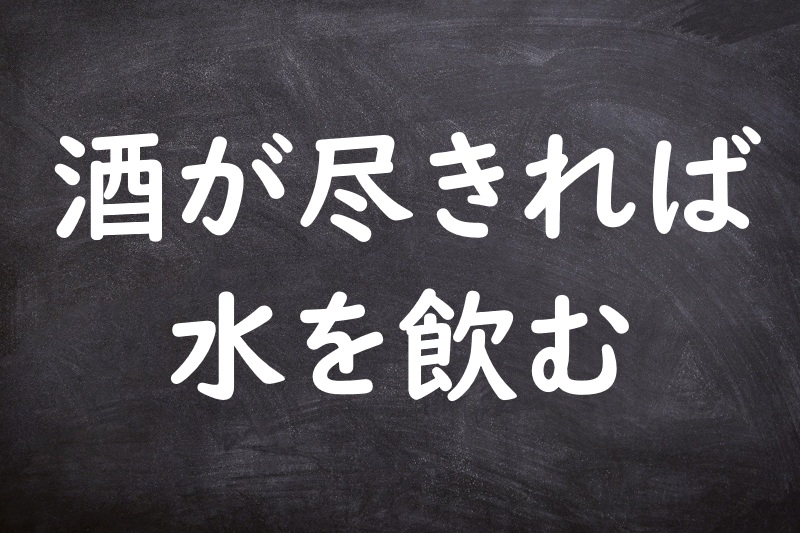 「さ」
「さ」 酒が尽きれば水を飲む(さけがつきればみずをのむ)
分類ことわざ意味飽きることを知らないことをいう。酒飲みは飲み尽くして酒が無くなれば、水でも飲むものである、ということから。
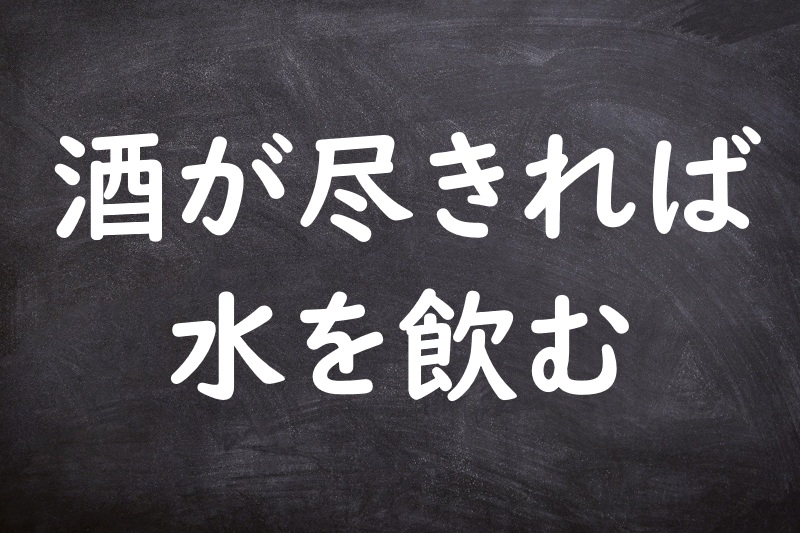 「さ」
「さ」 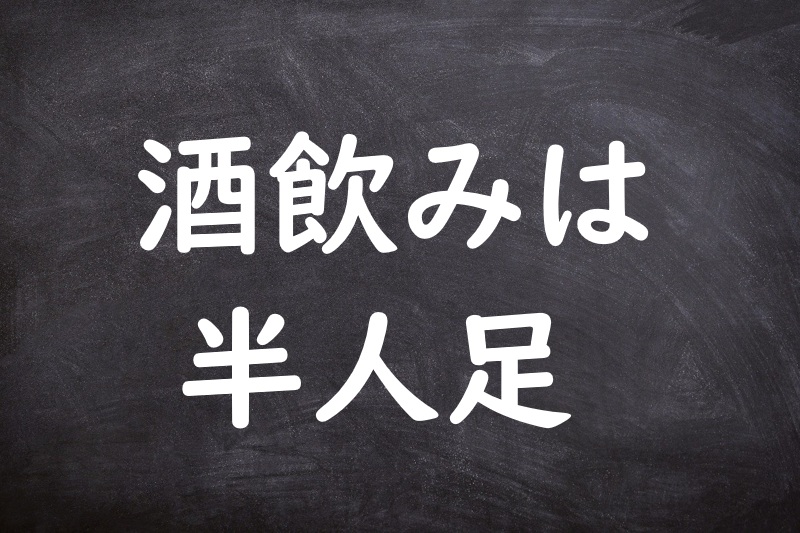 「さ」
「さ」 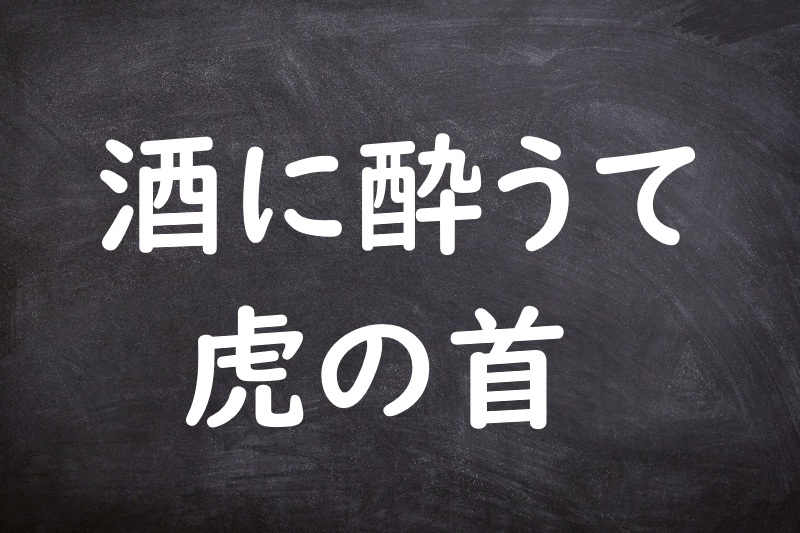 「さ」
「さ」 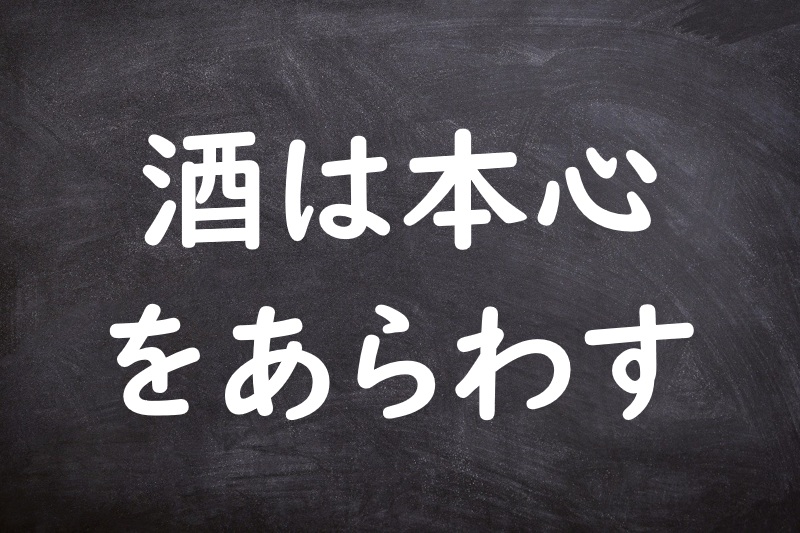 「さ」
「さ」 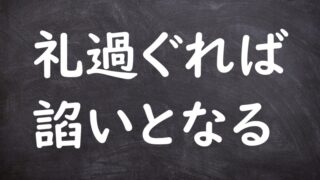 「れ」
「れ」 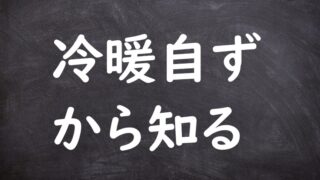 「れ」
「れ」 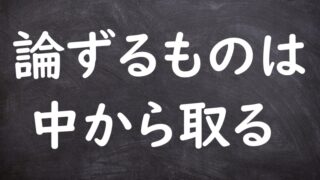 「ろ」
「ろ」 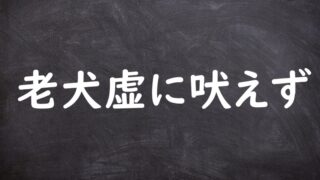 「ろ」
「ろ」 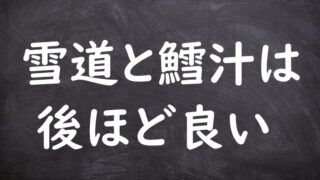 「ゆ」
「ゆ」 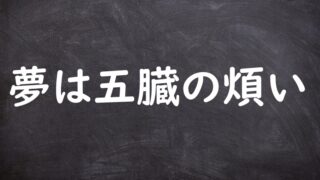 「ゆ」
「ゆ」 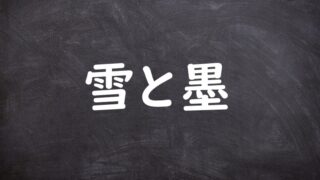 「ゆ」
「ゆ」 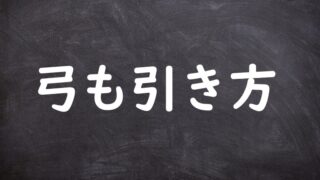 「ゆ」
「ゆ」 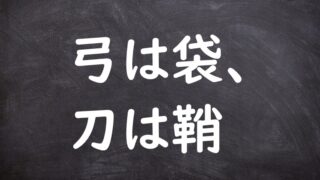 「ゆ」
「ゆ」  「た」
「た」 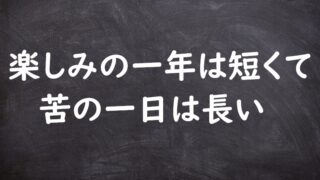 「た」
「た」 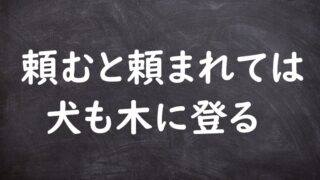 「た」
「た」 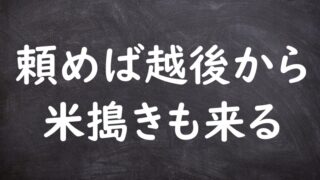 「た」
「た」 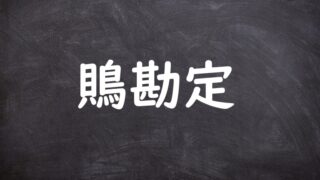 「も」
「も」 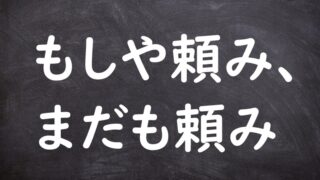 「も」
「も」 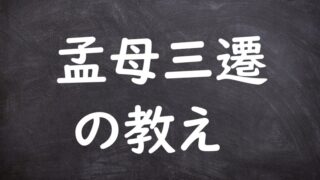 「も」
「も」