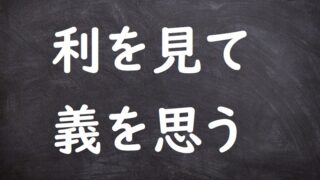 「り」
「り」 利を見て義を思う(りをみてぎをおもう)
分類ことわざ意味利益のあることも、義(義理)に合うか否かを考え、義に合えばその利益を取り、合わなければ取らないことをいう。『論語』にある句。
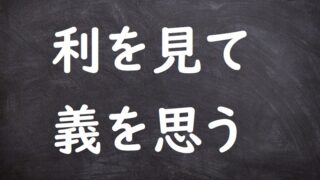 「り」
「り」 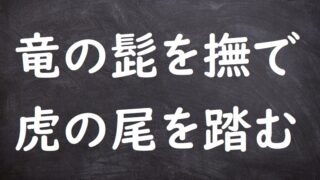 「り」
「り」 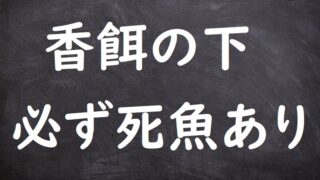 「こ」
「こ」  「こ」
「こ」 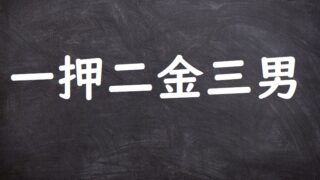 「い」
「い」 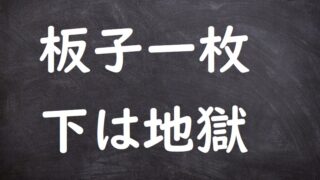 「い」
「い」 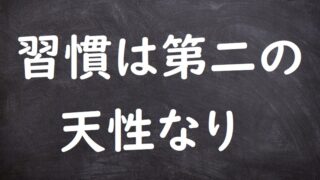 「し」
「し」 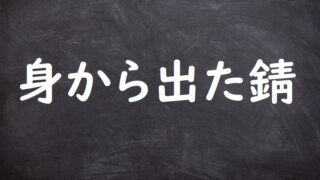 「み」
「み」 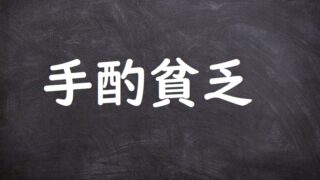 「て」
「て」 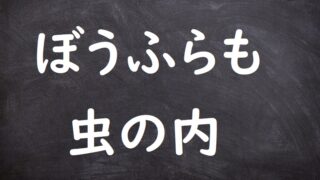 「ほ」
「ほ」 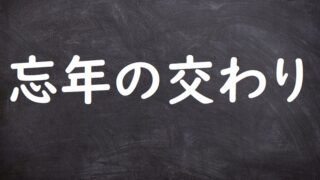 「ほ」
「ほ」 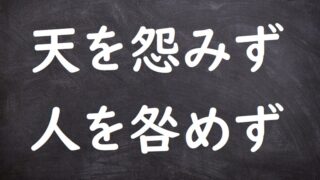 「て」
「て」 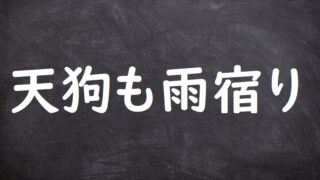 「て」
「て」 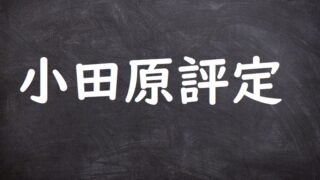 「お」
「お」 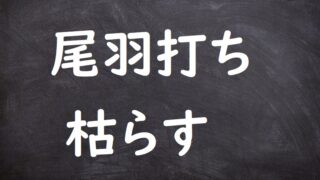 「お」
「お」 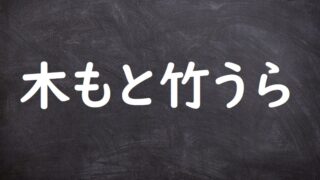 「き」
「き」 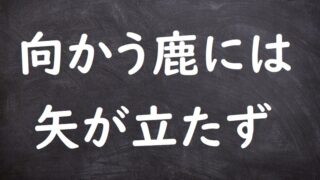 「む」
「む」 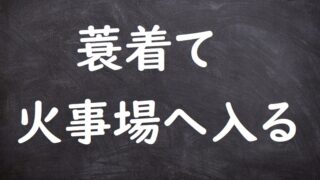 「み」
「み」 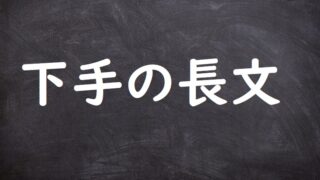 「へ」
「へ」 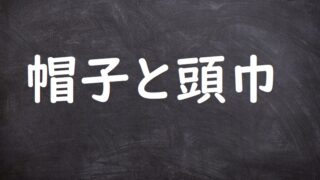 「ほ」
「ほ」