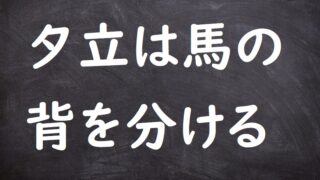 「ゆ」
「ゆ」 夕立は馬の背を分ける(ゆうだちはうまのせをわける)
分類ことわざ意味夕立が局地的に降ることを例えた言葉。夕立は、一頭の馬の背を、半分だけ濡らして降ったりするものである、ということから。ある場所では雨が降っているのに、ごく近い場所では晴れているということ。
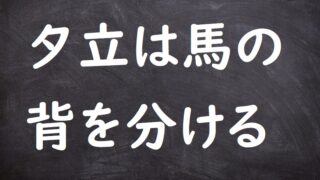 「ゆ」
「ゆ」 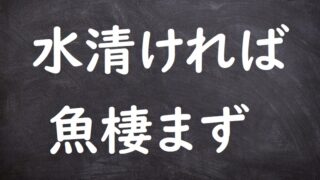 「み」
「み」 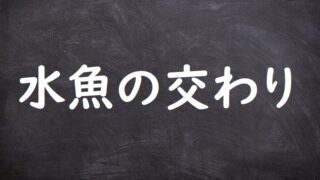 「す」
「す」 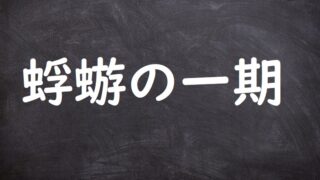 「ふ」
「ふ」 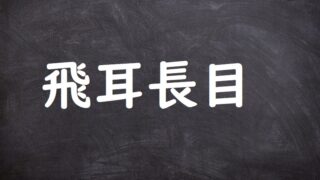 「ひ」
「ひ」 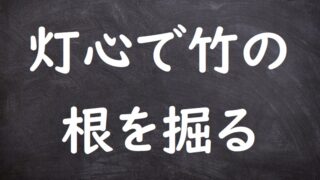 「と」
「と」 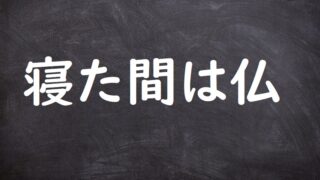 「ね」
「ね」 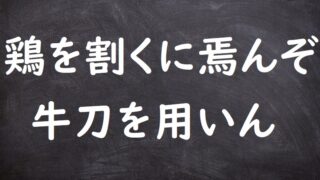 「に」
「に」 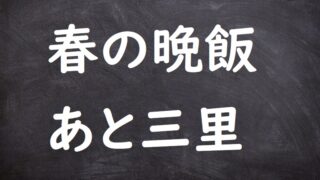 「は」
「は」 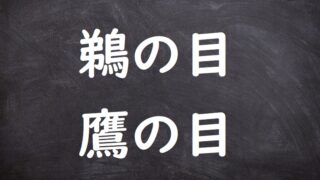 「う」
「う」 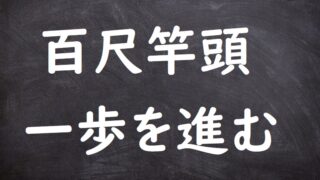 「ひ」
「ひ」 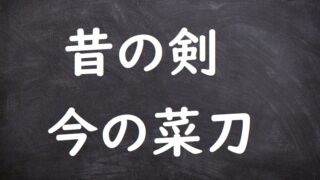 「む」
「む」 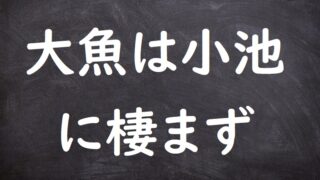 「た」
「た」 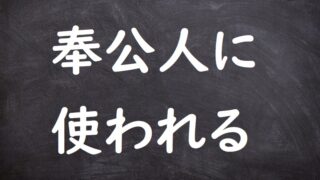 「ほ」
「ほ」 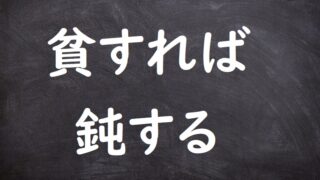 「ひ」
「ひ」 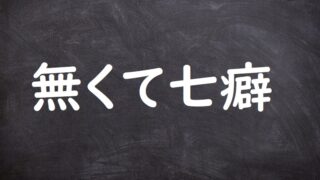 「な」
「な」 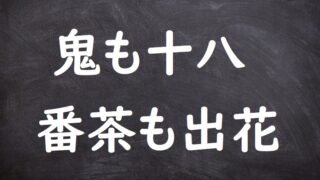 「お」
「お」 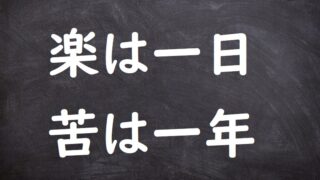 「ら」
「ら」 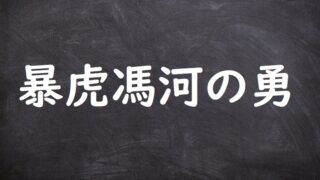 「ほ」
「ほ」 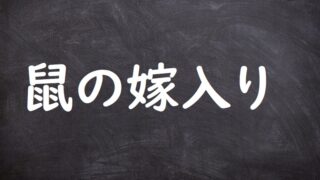 「ね」
「ね」