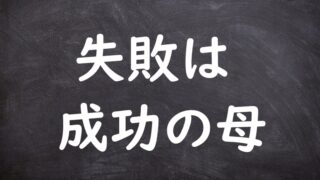 「し」
「し」 失敗は成功の母(しっぱいはせいこうのはは)
分類ことわざ意味失敗の原因をよく研究して改善すれば、次には成功させることができる。失敗こそが成功を生む、という意味。同類語・同義語失敗は成功の基(しっぱいはせいこうのもと)禍を転じて福と為す(わざわいをてんじてふくとなす)
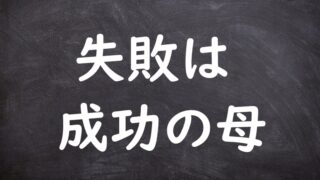 「し」
「し」 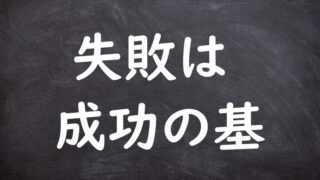 「し」
「し」 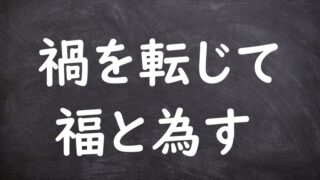 「わ」
「わ」 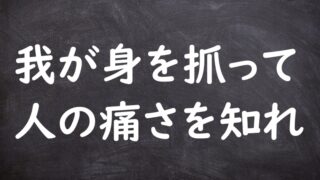 「わ」
「わ」 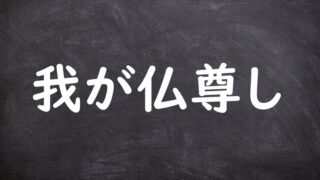 「わ」
「わ」 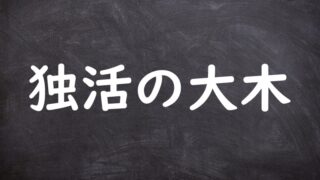 「う」
「う」 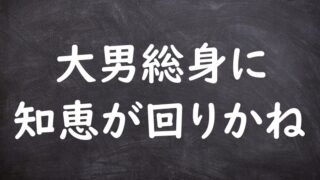 「お」
「お」 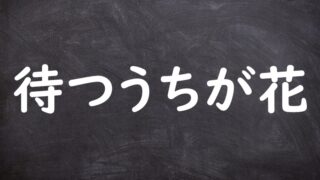 「ま」
「ま」 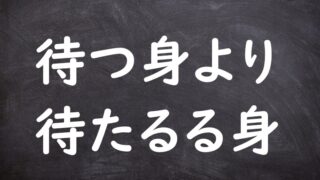 「ま」
「ま」 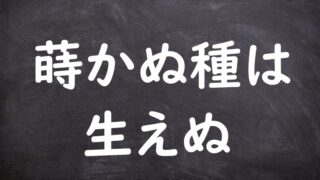 「ま」
「ま」 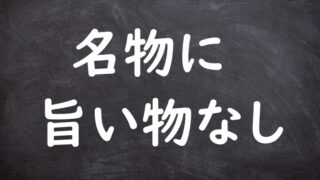 「め」
「め」 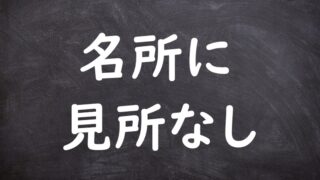 「め」
「め」 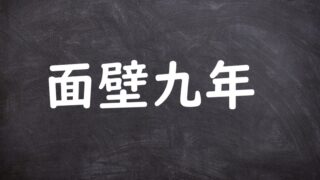 「め」
「め」 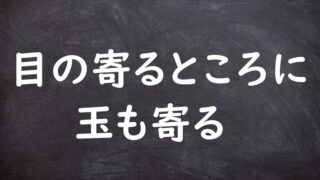 「め」
「め」 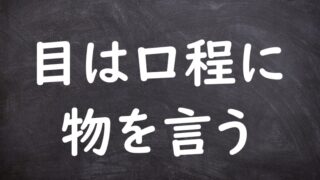 「め」
「め」 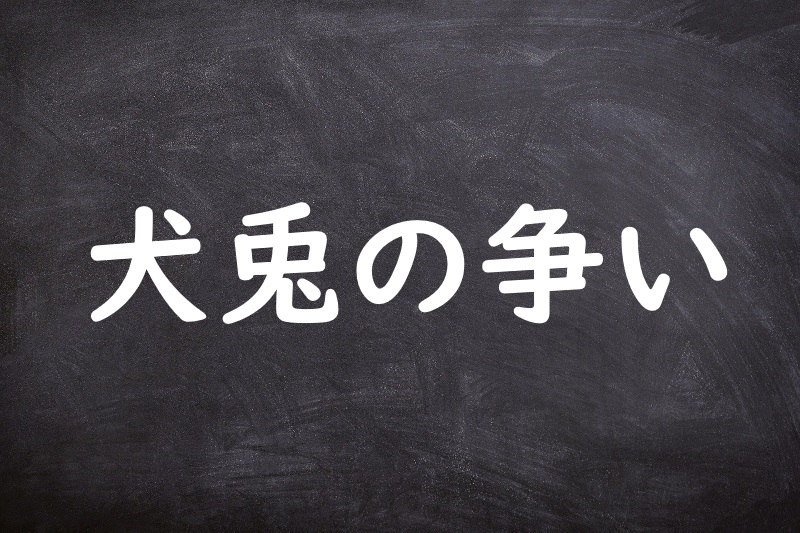 「け」
「け」 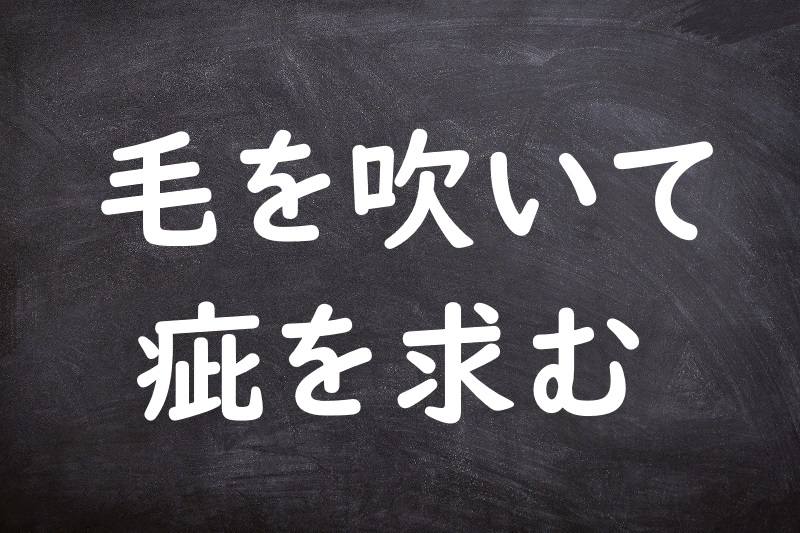 「け」
「け」 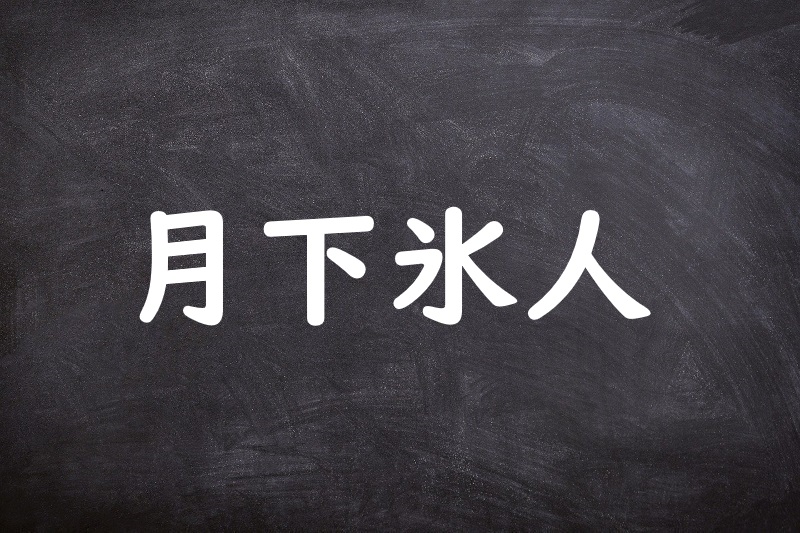 「け」
「け」 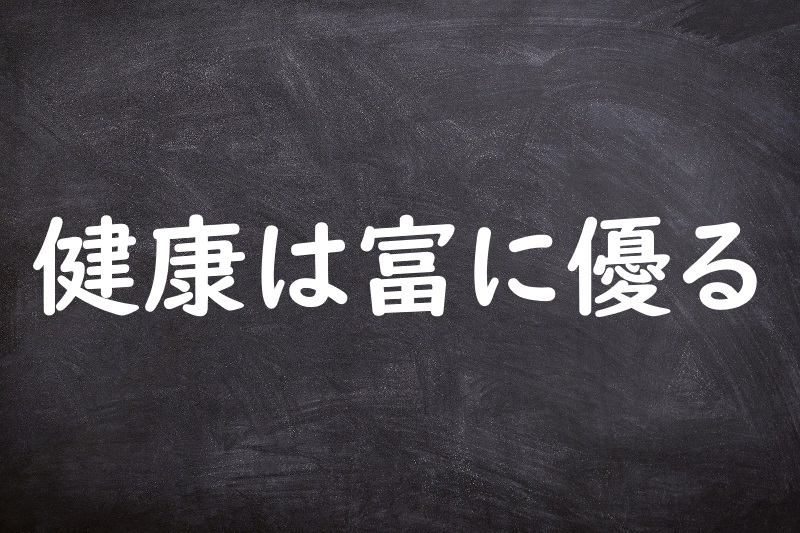 「け」
「け」 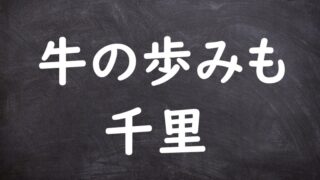 「う」
「う」