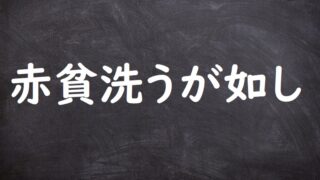 「せ」
「せ」 赤貧洗うが如し(せきひんあらうがごとし)
分類ことわざ意味大変な貧乏で、水で洗い流したように何一つ財産を所持していない様子のこと。「赤貧」は何一つ持たずに丸裸のように貧しい様子の事。ここでの「赤」は、裸の意味。
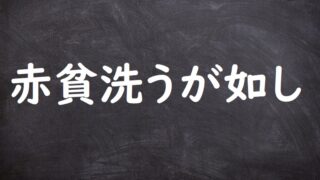 「せ」
「せ」 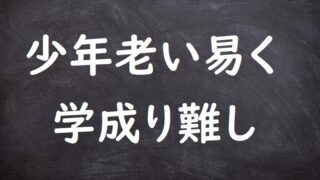 「し」
「し」 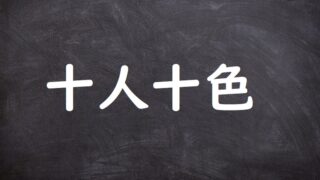 「し」
「し」 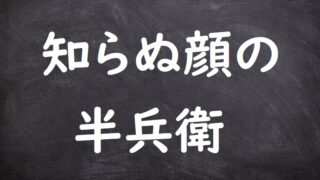 「し」
「し」 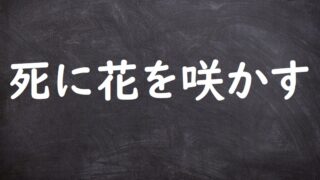 「し」
「し」 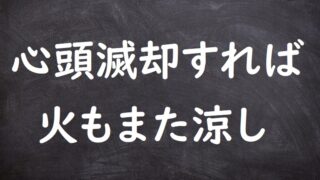 「し」
「し」 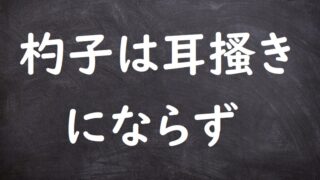 「し」
「し」 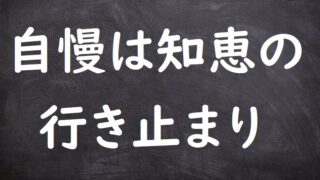 「し」
「し」 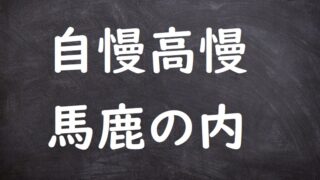 「し」
「し」 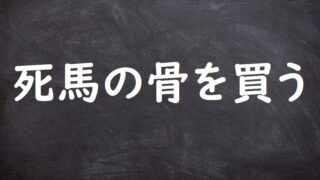 「し」
「し」 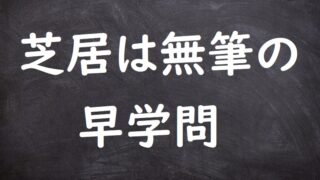 「し」
「し」 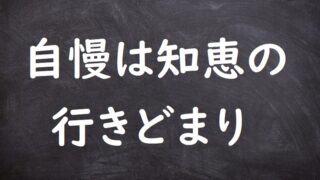 「し」
「し」 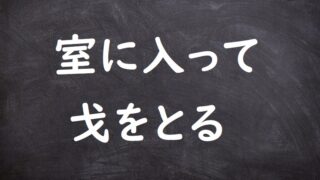 「し」
「し」 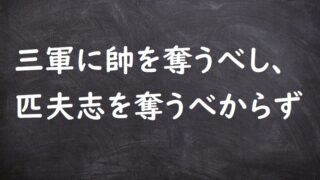 「さ」
「さ」 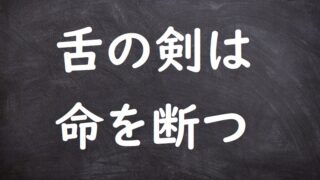 「し」
「し」 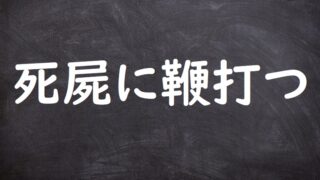 「し」
「し」 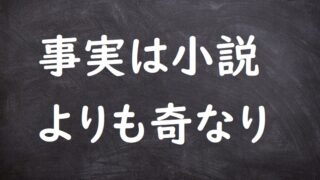 「し」
「し」 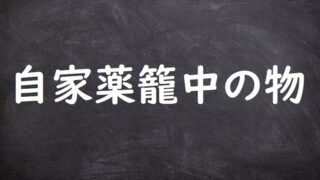 「し」
「し」 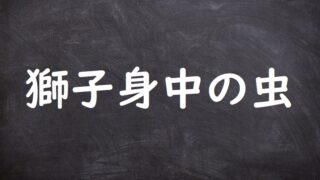 「し」
「し」 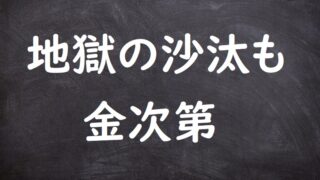 「し」
「し」