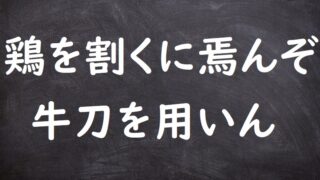 「に」
「に」 鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん(にわとりをさくにいずくんぞぎゅうとうをもちいん)
分類ことわざ意味些細な事を処理するのに、大袈裟な方法を用いる必要はない、という意味。用い方・用法が誤っていることのたとえ。鶏を料理するのに、牛を切る時に使用する大きな包丁を使う必要はない、ということから。論語にある言葉。同類語・同義語 鶏を...
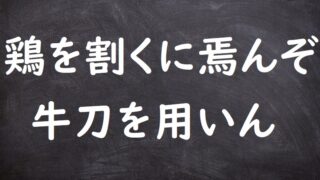 「に」
「に」 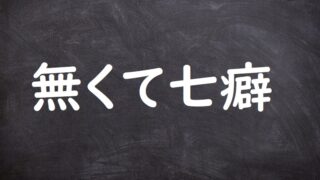 「な」
「な」 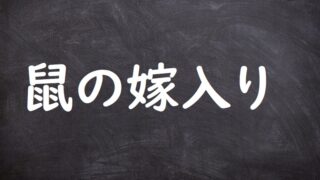 「ね」
「ね」 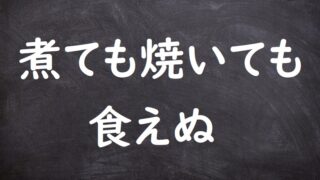 「に」
「に」 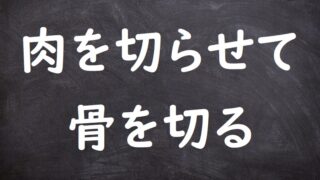 「に」
「に」 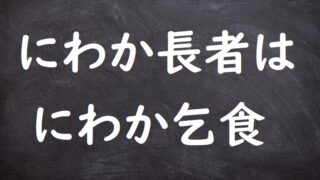 「に」
「に」 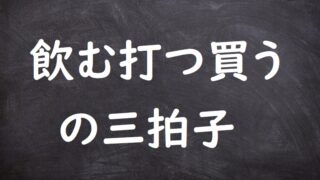 「の」
「の」 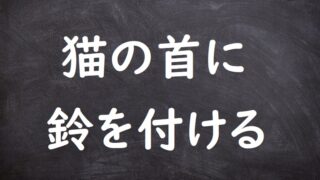 「ね」
「ね」 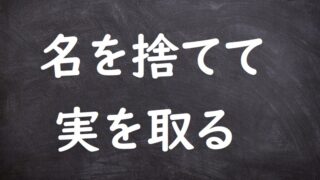 「な」
「な」 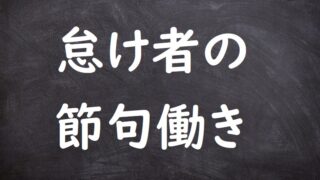 「な」
「な」 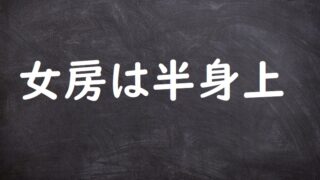 「に」
「に」 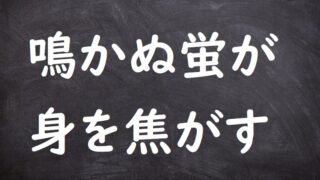 「な」
「な」 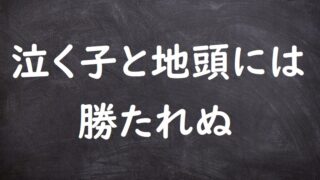 「な」
「な」 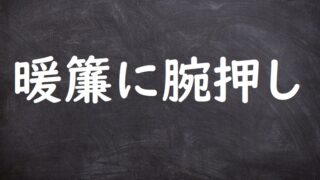 「の」
「の」 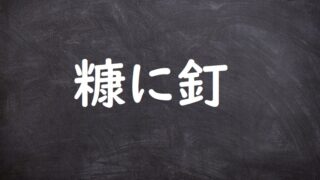 「ぬ」
「ぬ」 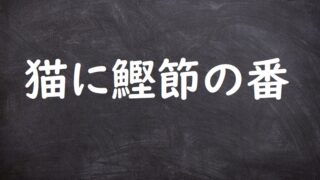 「ね」
「ね」 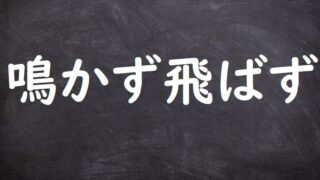 「な」
「な」 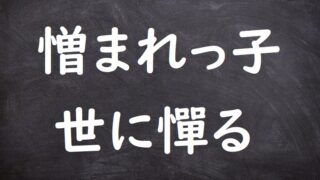 「に」
「に」 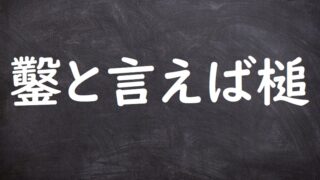 「の」
「の」 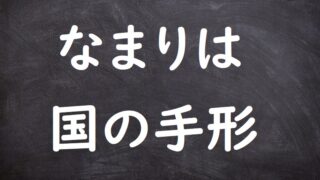 「な」
「な」