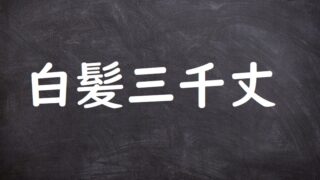 「は」
「は」 白髪三千丈(はくはつさんぜんじょう)
分類ことわざ意味度重なる心労や悲嘆のために、頭髪が白くなり驚くほど長く伸びてしまった、という意味。誇張された表現、または大げさな表現の例として言われる。李白の詩句より。一丈は約3.1メートルで、三千丈は9300メートル。白髪が長く伸びたこと...
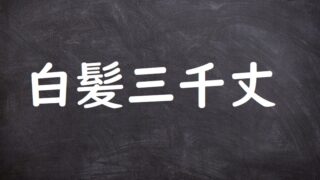 「は」
「は」 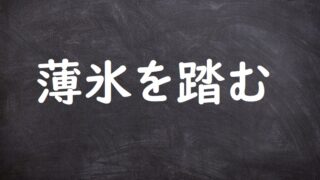 「は」
「は」 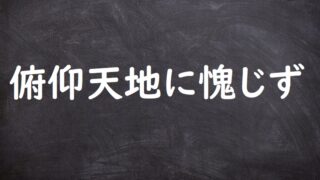 「ふ」
「ふ」 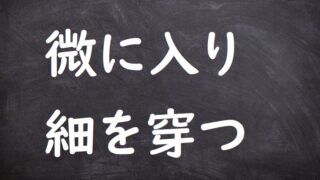 「ひ」
「ひ」 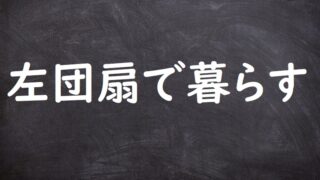 「ひ」
「ひ」 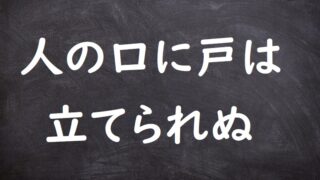 「ひ」
「ひ」 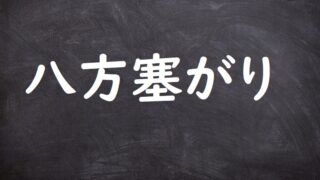 「は」
「は」 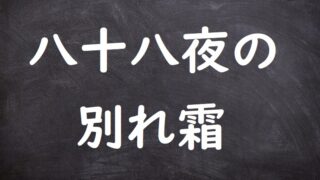 「は」
「は」 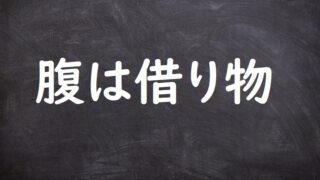 「は」
「は」 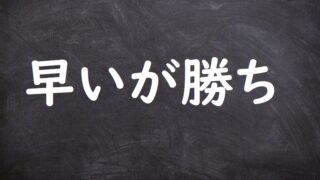 「は」
「は」 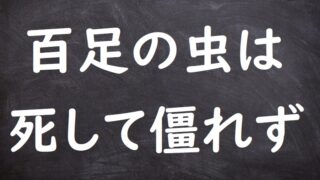 「ひ」
「ひ」 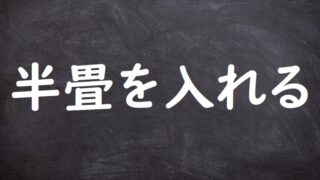 「は」
「は」 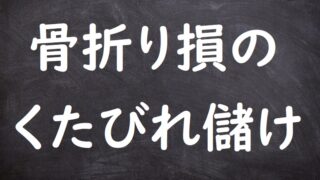 「ほ」
「ほ」 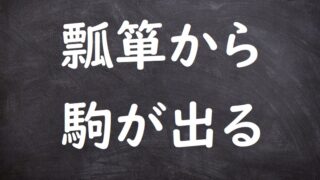 「ひ」
「ひ」 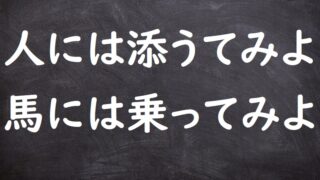 「ひ」
「ひ」 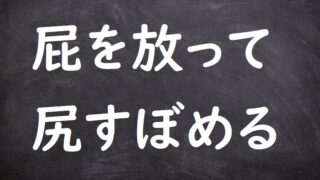 「へ」
「へ」 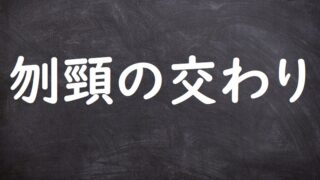 「ふ」
「ふ」 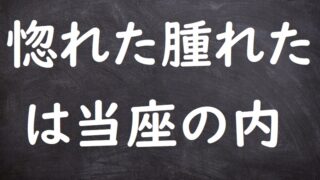 「ほ」
「ほ」 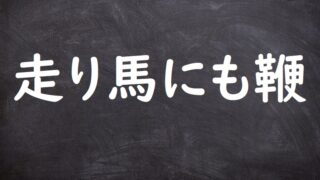 「は」
「は」 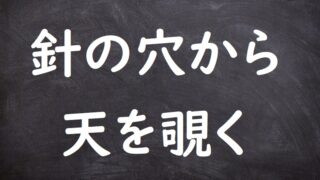 「は」
「は」