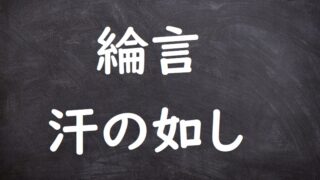 「り」
「り」 綸言汗の如し(りんげんあせのごとし)
分類ことわざ意味一度体外に出た汗が二度と身体に戻ることがないように、一度出せれた天皇陛下の言葉は、取り消したり、改めたりできないものだ、という意味。「綸言」とは、帝王の言葉のたとえ。
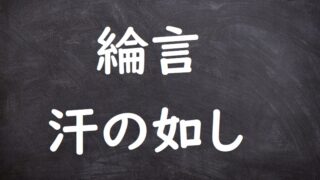 「り」
「り」 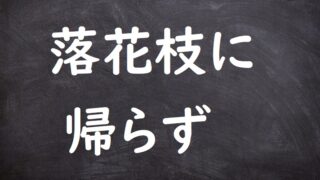 「ら」
「ら」 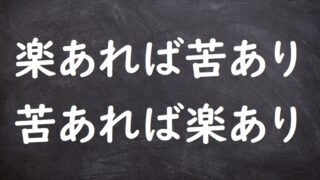 「ら」
「ら」 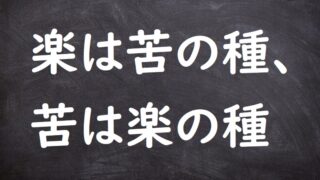 「ら」
「ら」 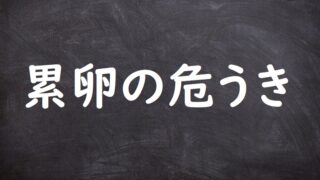 「る」
「る」 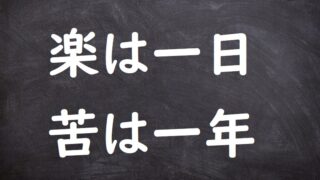 「ら」
「ら」 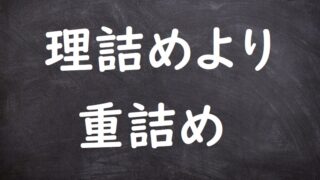 「り」
「り」 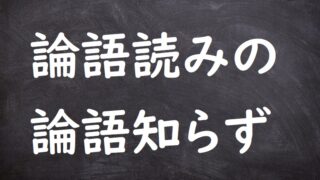 「ろ」
「ろ」 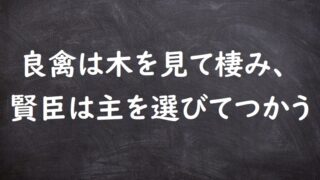 「り」
「り」 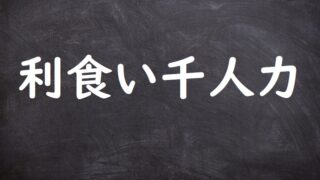 「り」
「り」 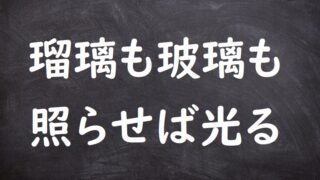 「る」
「る」 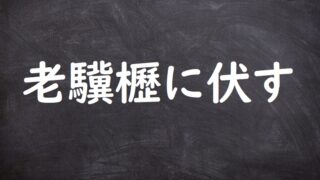 「ろ」
「ろ」 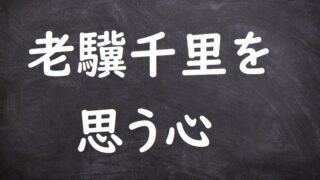 「ろ」
「ろ」 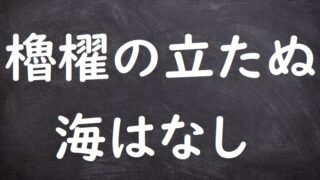 「ろ」
「ろ」 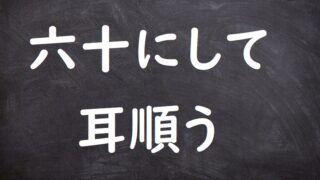 「ろ」
「ろ」 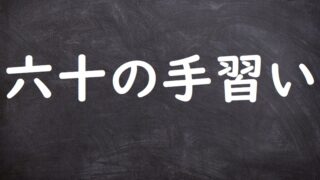 「ろ」
「ろ」 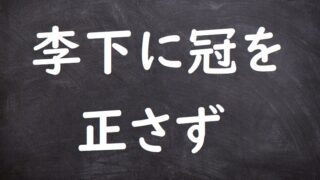 「り」
「り」 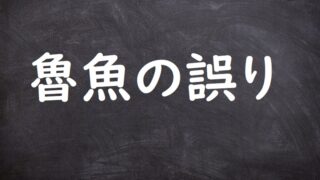 「ろ」
「ろ」 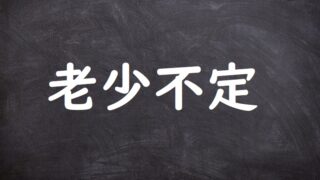 「ろ」
「ろ」 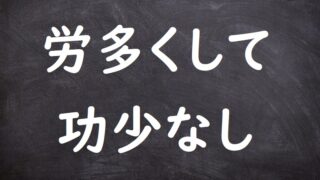 「ろ」
「ろ」