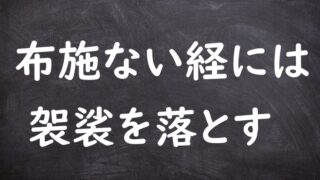 「ふ」
「ふ」 布施ない経には袈裟を落とす(ふせないきょうにはけさをおとす)
分類ことわざ意味報酬が少ないと仕事にも熱が入らず勤めるところも薄い、という意味。お布施をくれない貰わないときには、僧侶は、略式でお経を読むのにも袈裟を身に着けない、ということから。同類語・同義語 布施ない経に袈裟落とす(ふせないきょうにけさ...
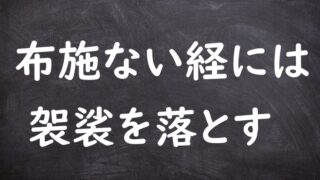 「ふ」
「ふ」 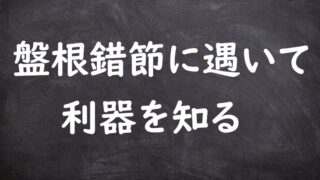 「は」
「は」 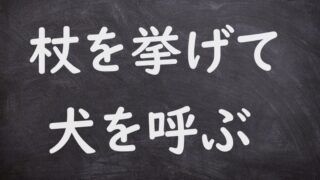 「つ」
「つ」 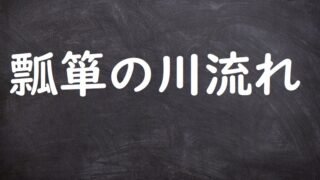 「ひ」
「ひ」 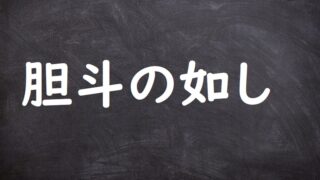 「た」
「た」 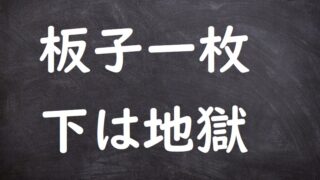 「い」
「い」 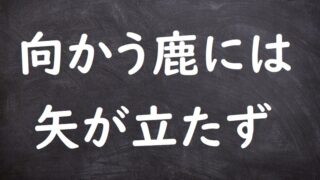 「む」
「む」 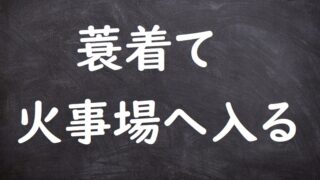 「み」
「み」 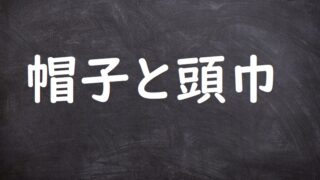 「ほ」
「ほ」 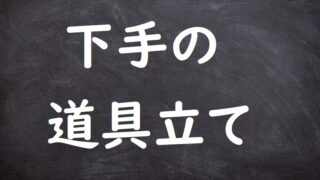 「へ」
「へ」 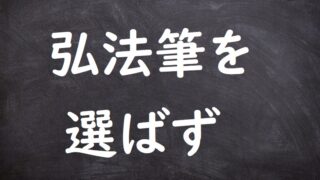 「こ」
「こ」 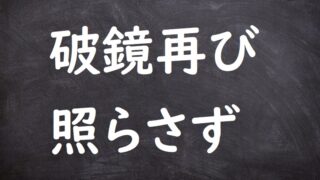 「は」
「は」 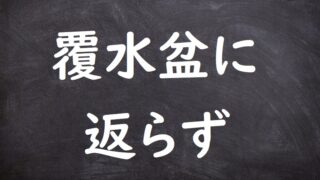 「ふ」
「ふ」 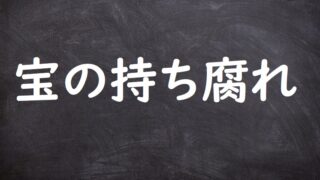 「た」
「た」 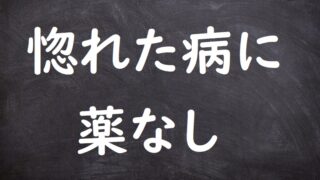 「ほ」
「ほ」 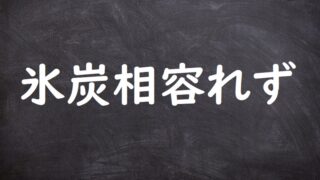 「ひ」
「ひ」 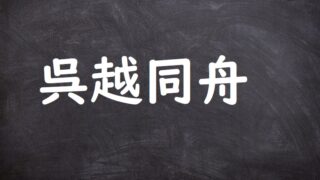 「こ」
「こ」 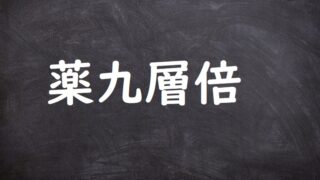 「く」
「く」 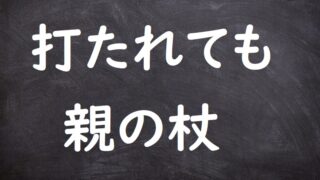 「う」
「う」 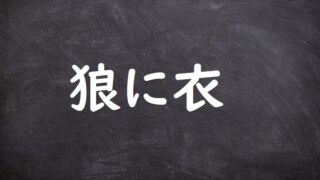 「お」
「お」