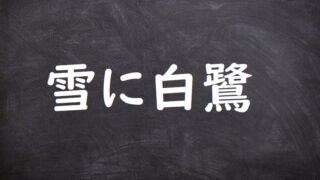 「ゆ」
「ゆ」 雪に白鷺(ゆきにしらさぎ)
分類ことわざ意味見分けにくいことをいう。また、目立たないことをいう。白い雪の中に、これまた白い鷺である白鷺がいる、ということから。
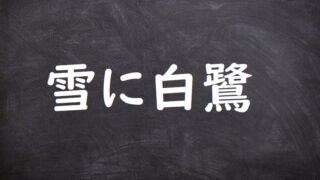 「ゆ」
「ゆ」 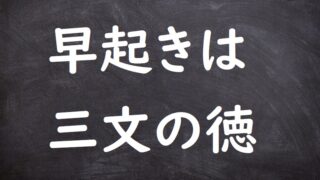 「は」
「は」 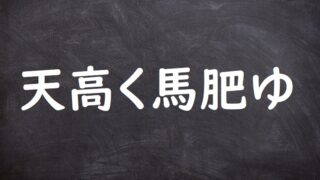 「て」
「て」 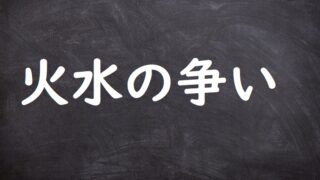 「ひ」
「ひ」 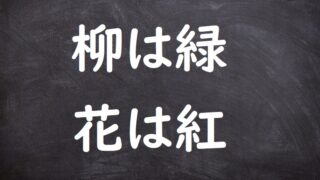 「や」
「や」 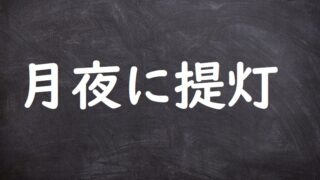 「つ」
「つ」 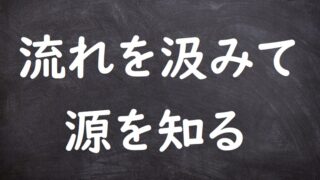 「な」
「な」 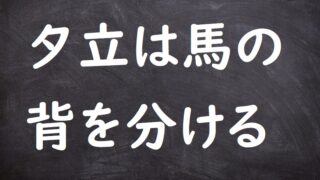 「ゆ」
「ゆ」 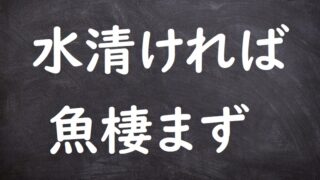 「み」
「み」 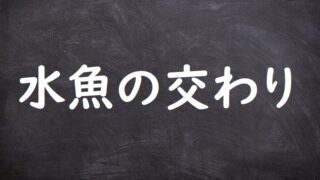 「す」
「す」 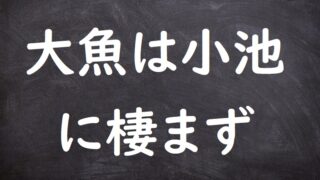 「た」
「た」 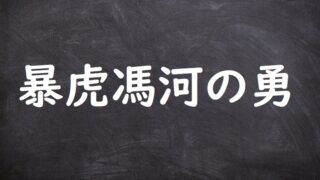 「ほ」
「ほ」 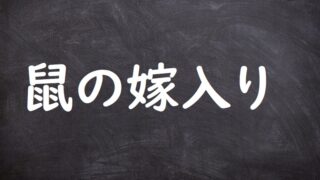 「ね」
「ね」 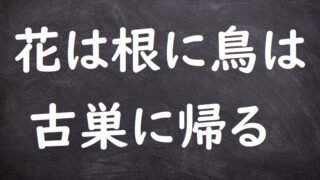 「は」
「は」 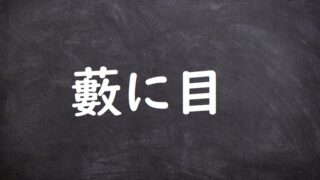 「や」
「や」 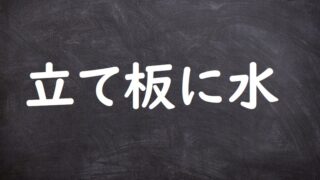 「た」
「た」 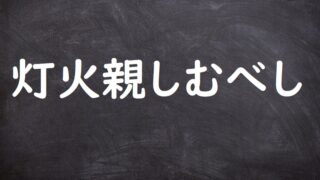 「と」
「と」 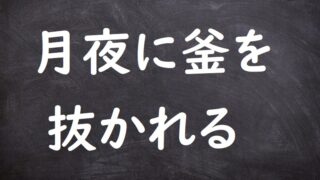 「つ」
「つ」 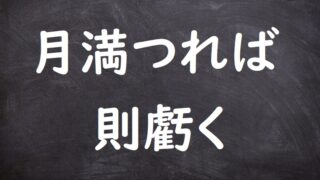 「つ」
「つ」 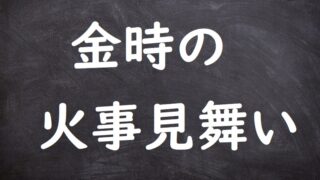 「き」
「き」