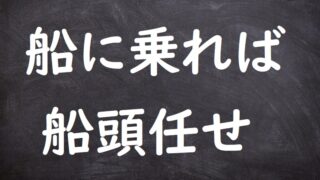 「ふ」
「ふ」 船に乗れば船頭任せ(ふねにのればせんどうまかせ)
分類ことわざ意味物事はそれぞれの専門家に任せるのが良い、という意味。誰でもいったん船に乗ってしまえば、すべて船頭に任せるのが賢明であることから、どんなことでもその道の専門家に任せるのが良い、ということ。同類語・同義語 船は船頭に任せよ(ふね...
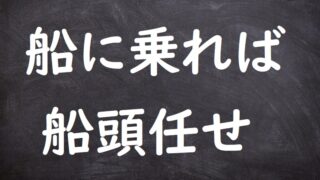 「ふ」
「ふ」 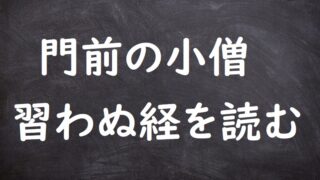 「も」
「も」 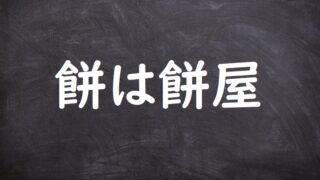 「も」
「も」 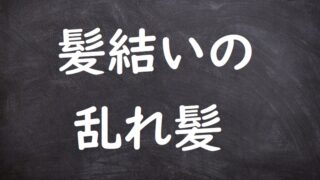 「か」
「か」 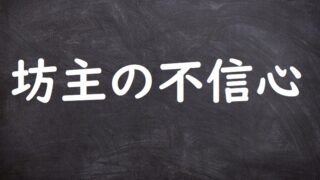 「ほ」
「ほ」 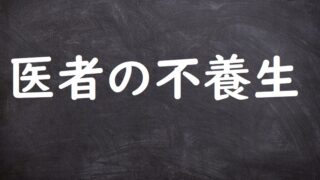 「い」
「い」 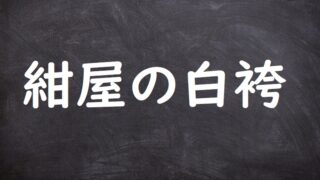 「こ」
「こ」 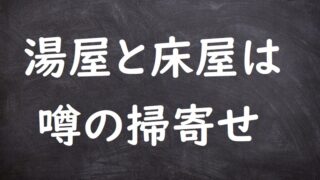 「ゆ」
「ゆ」 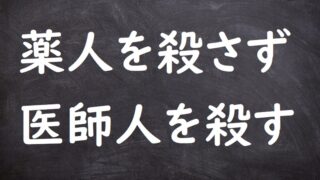 「く」
「く」 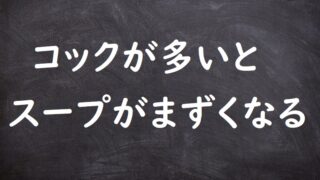 「こ」
「こ」 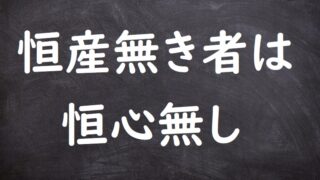 「こ」
「こ」 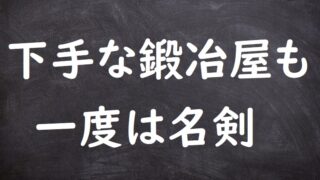 「へ」
「へ」 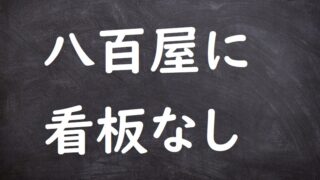 「や」
「や」 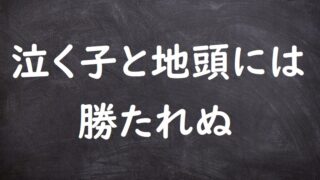 「な」
「な」 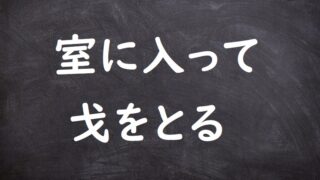 「し」
「し」 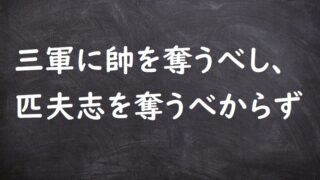 「さ」
「さ」 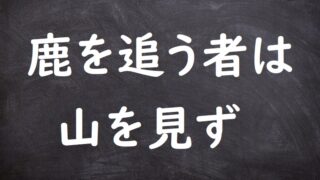 「し」
「し」 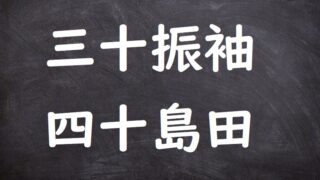 「さ」
「さ」 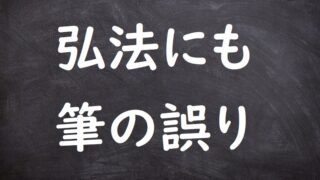 「こ」
「こ」 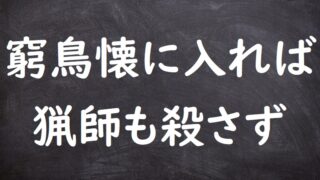 「き」
「き」