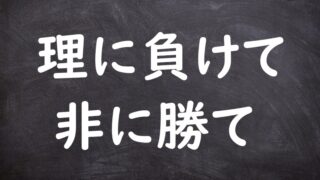 「り」
「り」 理に負けて非に勝て(りにまけてひにかて)
分類ことわざ意味道理や理屈には負けてもよいが、不利益な立場には立たないようにし実利を取ることが大事である、という意味。「非」は、自分に不利な状態のこと。同類語・同義語理に勝ちて非に負ける(りにかちてひにまける)理に勝って非に落ちる(りにかっ...
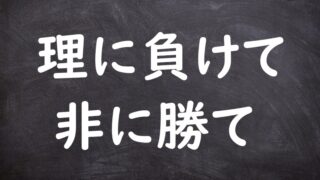 「り」
「り」 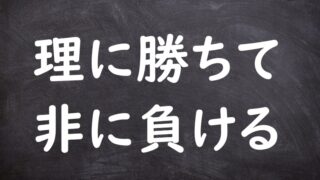 「り」
「り」 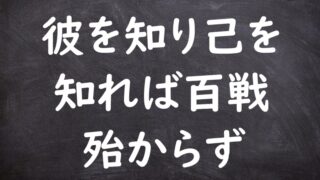 「か」
「か」 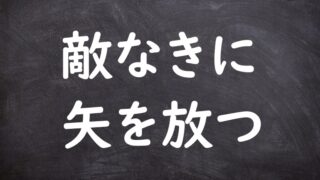 「て」
「て」 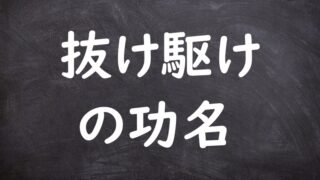 「ぬ」
「ぬ」 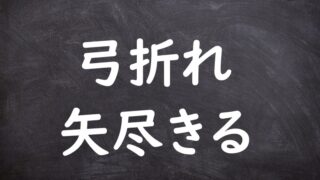 「ゆ」
「ゆ」 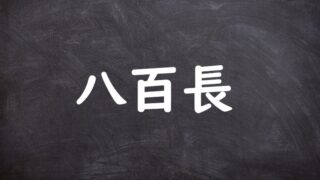 「や」
「や」 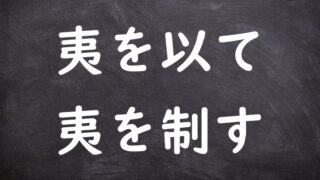 「い」
「い」 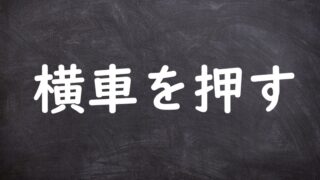 「よ」
「よ」 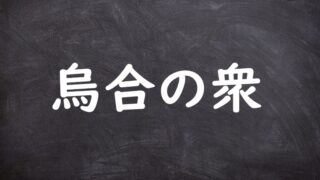 「う」
「う」 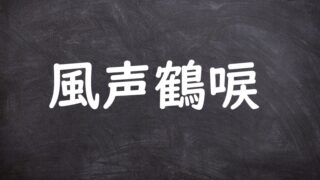 「ふ」
「ふ」 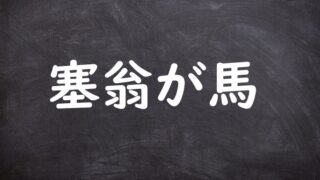 「さ」
「さ」 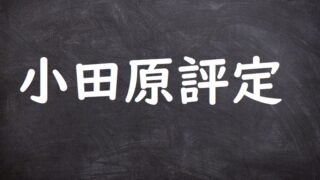 「お」
「お」 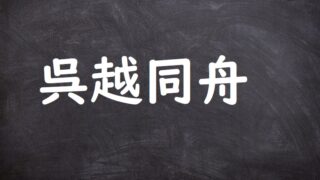 「こ」
「こ」 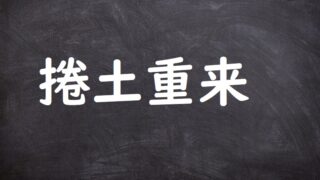 「け」
「け」 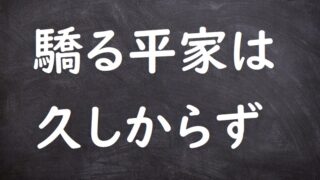 「お」
「お」 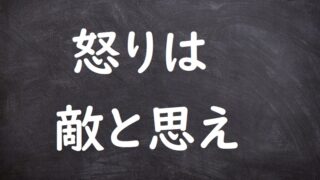 「い」
「い」 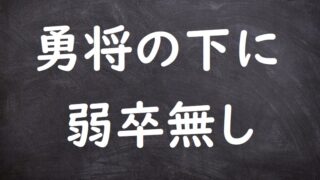 「ゆ」
「ゆ」 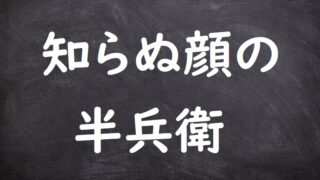 「し」
「し」 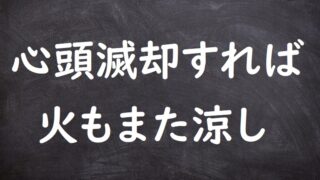 「し」
「し」