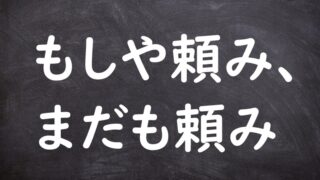 「も」
「も」 もしや頼み、まだも頼み(もしやたのみ、まだもたのみ)
分類ことわざ意味万一の幸運を願う心のこと。もしやと思っては望みをかけ、まだまだと思っては頼みにする、ということから。
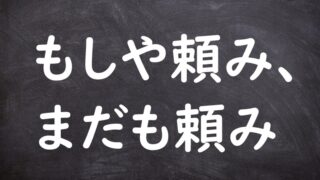 「も」
「も」 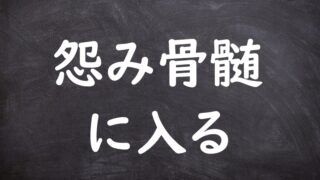 「う」
「う」 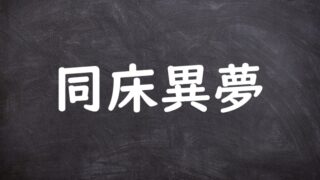 「と」
「と」 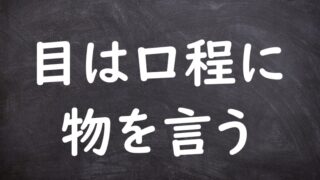 「め」
「め」 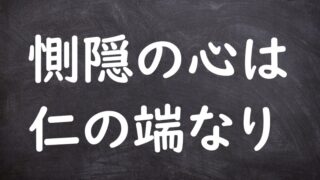 「そ」
「そ」 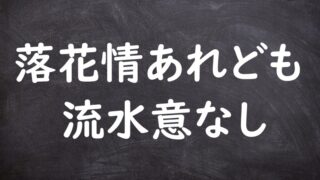 「ら」
「ら」 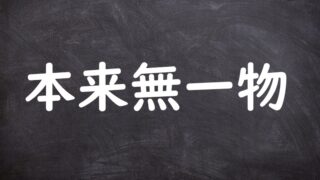 「ほ」
「ほ」 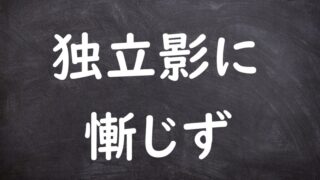 「と」
「と」 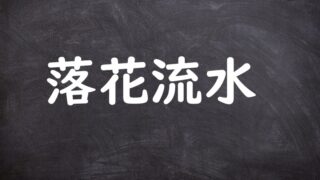 「ら」
「ら」 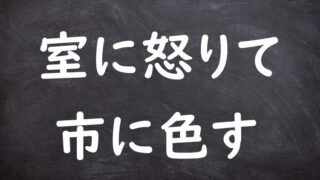 「し」
「し」 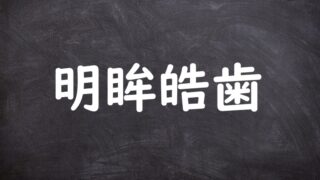 「め」
「め」 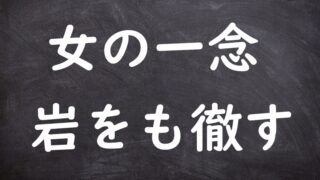 「お」
「お」 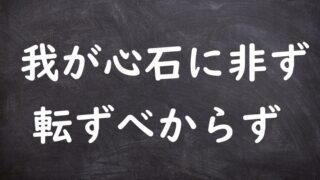 「わ」
「わ」 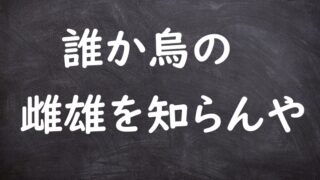 「た」
「た」 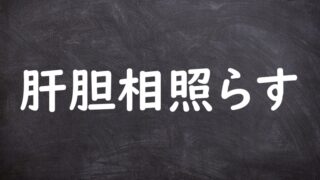 「か」
「か」 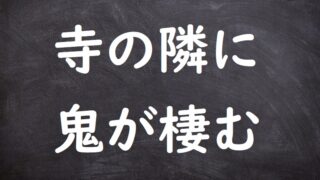 「て」
「て」 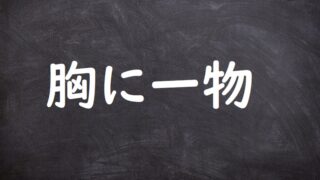 「む」
「む」 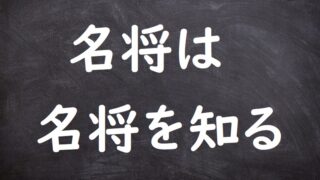 「め」
「め」 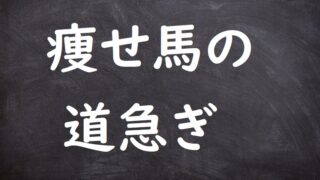 「や」
「や」 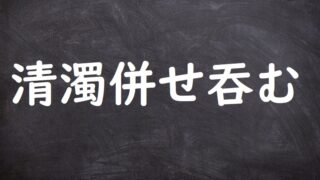 「せ」
「せ」