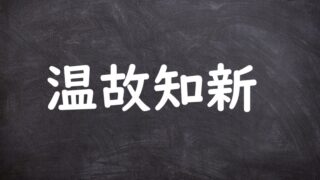 「お」
「お」 温故知新(おんこちしん)
分類ことわざ意味昔のことや古い事柄を研究して、そこから新しい真理を発見すること。「温」は、復習すること。「故」は、古い事柄。『論語』で孔子が教師の資格として述べた言葉。同類語・同義語故きを温ねて新しきを知る(ふるきをたずねてあたらしきをしる...
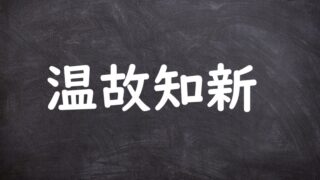 「お」
「お」 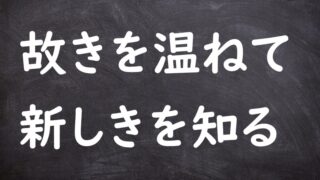 「ふ」
「ふ」 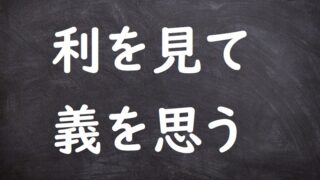 「り」
「り」 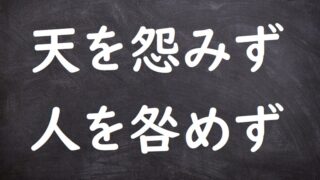 「て」
「て」 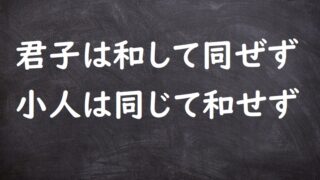 「く」
「く」 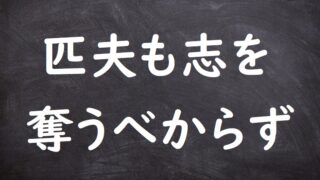 「ひ」
「ひ」 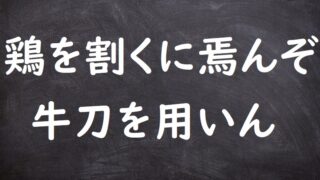 「に」
「に」 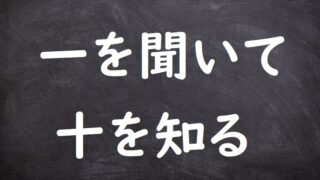 「い」
「い」 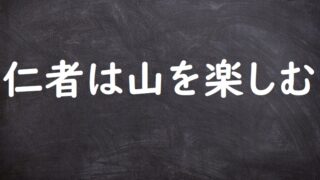 「し」
「し」 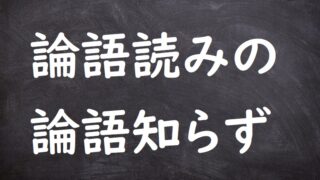 「ろ」
「ろ」 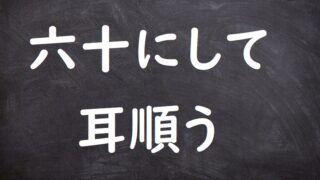 「ろ」
「ろ」